カテゴリ「詩誌」の224件の記事 
2016年8月31日 (水)
2016年8月12日 (金)
茨木のり子「対話」
 花神社「茨木のり子全詩集」(2013年・2刷)より、第1詩集「対話」を読みおえる。
花神社「茨木のり子全詩集」(2013年・2刷)より、第1詩集「対話」を読みおえる。
全詩集の購入は、今年2月27日の記事(←リンクしてある)にアップした。購入に至る経過を書いたので、是非読んでいただきたい。
「対話」は、1955年、不知火社・刊。
彼女は1926年、医師の長女として生まれ、19歳の時に敗戦、23歳で医師と結婚。
24歳頃に「詩学研究会」に投稿を始め、1953年(27歳頃)に詩誌「櫂」創刊に参加。第1詩集の発行に続く。
「根府川の海」では、動員時代への哀憐と反発心を描く。
「ひそかに」では、「ついに/永遠の一片をも掠め得なかった民族よ」と、帰還兵を嘆くけれども、戦後文学の隆盛を、否定する気持ちがあったのだろうか。
「或る日の詩」「小さな渦巻」が、詩作を語るに至る作品なのは、初期過ぎて危ぶむ。
2016年6月12日 (日)
季刊「ココア共和国」vol.19
 宮城県・在住の詩人、秋亜綺羅さんが個人詩誌、「ココア共和国」vol.19を送って下さった。
宮城県・在住の詩人、秋亜綺羅さんが個人詩誌、「ココア共和国」vol.19を送って下さった。
ツイッター上で同号を発行のニュースは流れたが、詩誌「群青」終刊後は送ってもらえないかと思っていたが、思いがけなく同号が届き、ここで紹介するまで日数を経てしまった。
同誌・vol.18は、昨年12月17日付けの記事(←リンクしてある)で紹介した。
招待の中家菜津子さんの詩・短歌「筆箱」、打田峨者んさんの俳句「風の再話――昔むかしのどの昔」は、作品の良さが僕にもわかる。
詩の招待作品が、僕にはわからない。僕が現代日本詩の最前線より遠く長く、離れているせいだろう。
松尾真由美さん「崩れさるもの、巣の渾沌」、橋本シオンさん「デストロイしている」の題名が示しているように、都会の人の心は崩れ、壊れているのだろうか。
秋亜綺羅さんの「凱歌」ほか2編は、2行1連を繰り返しており、定型への志向が読める。彼は否定するけれど、戦後詩の流れを汲むと、僕は思っている。エッセイも有意義である。
2016年5月11日 (水)
2016年4月 9日 (土)
詩誌「果実」74号
 先日、同人詩誌「果実」の編集・発行人、T・篤朗さんより、お便りをそえて同誌・74号を頂いた。
先日、同人詩誌「果実」の編集・発行人、T・篤朗さんより、お便りをそえて同誌・74号を頂いた。
2016年4月、果実の会・刊。
6名18編の詩と、3名3編の評論・詩論を収める。
N・昌弘さんの「パンドラの小箱」は、USBメモリがクラッシュした後を描いているようだが、余裕のある所にユーモアを感じる。
W・本爾さんの散文詩「ときに父を想う」は、情の優しかった父を偲んで、真実の姿を捉えた。
F・則行さんの童話風な散文詩「さざんか」「野菊」は、僕は苦手である。高く評価する読者もいるだろう。
T・篤朗さんは、6編の詩を寄せている。「階段」の寓喩、「確かなもの」のリフレイン、「行ってしまった」の観念性、等いずれも真実を衝いている。
2016年4月 7日 (木)
詩誌「青魚」No.84
 僕の参加している同人詩誌「青魚(せいぎょ)」の、No.84が千葉・発行人より送られてきた。
僕の参加している同人詩誌「青魚(せいぎょ)」の、No.84が千葉・発行人より送られてきた。
2016年4月5日・刊。B・5判、2段組み、35ページ。
僕は「治ったものとそうでないもの」以下、6編のソネット(のようなもの)を、巻頭に載せてもらった。
もう1つのブログ、「新サスケと短歌と詩」(←リンクしてある)の、4月4日以後の記事で、毎日1編ずつ紹介している(横書きになり、1部推敲してある)。
T・幸男さんの「ツイッター」以下6編が、独特のボキャブラリィを用いて、社会を批判し続けている。
また同人・山本修三さんへの追悼文、2編を載せる。
この詩誌「青魚」にも、散文が多くなってきていると、危惧する。
2016年4月 6日 (水)
2016年1月30日 (土)
同人詩誌「群青」合本
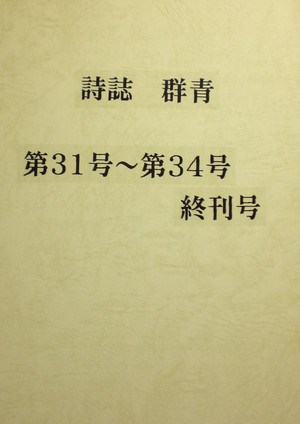 同人詩誌「群青」同人のAUさんが、31号で抜け、残った相棒のこぐま星座さんより年賀状で「『群青』での活動をしばらく休みたい」と申し出があり、2015年11月・刊の第34号で終刊し、母体の「群青の会」も解散する事にした。
同人詩誌「群青」同人のAUさんが、31号で抜け、残った相棒のこぐま星座さんより年賀状で「『群青』での活動をしばらく休みたい」と申し出があり、2015年11月・刊の第34号で終刊し、母体の「群青の会」も解散する事にした。
最後はこぐま星座さんが詩人らしく、きれいに纏めてくれた。
第31号~第34号の合本を2部、宮本印刷で作成してもらい(無料で)、1部をこぐま星座さんに郵送した。(表題は家のテーププリンターで)。
直近の同誌・第21号~第30号の合本は、2014年7月9日の記事(←リンクしてある)にアップした。
2004年10月に創刊号を発行し、通巻して僕とこぐま星座さんと女性3人が同人となったが、女性詩人が続かない欠点があった。
詩才あるこぐま星座さんに、発表の場を、という意向で創刊した詩誌なので、先述の事態となり、潔く終刊・解散を決めた。
11年余に関わってくださった方々に、感謝の意を表する。
2016年1月19日 (火)
詩誌「水脈」55号
2015年11月・刊。
同誌・54号は、昨年9月21日の記事(←リンクしてある)で紹介した。
大所帯のグループの強さを思う。1部の会員が去っても、ある会員が病気で休んでも、グループの活動は続いて行く。
扉詩に次ぐ巻頭の、H・はつえさんの「ひつじ雲」の冒頭、「秋空の高い雲の間に/ひつじを数匹ばかり放してきた/そうすると数日中に一匹残らずいなくなる/生贄になるひつじ達/大空では信じがたい惨事が起きている//…」と始まる。
それに次ぐ、N・千代子さんの「ヒトは表現する生き物」では第3連、「体験と感受性だけでは/詩は書けないようだ/…/踏みとどまって技を鍛えることも必要か/…」とある。
同誌の作品が、レトリカルに、フィクショナルになっているようだ。僕の思い違いか。詩壇の流れか。誰かの発案か。
まやかしの言葉のはびこる現在こそ、リアリズムの言葉で抵抗すべきではないのか。いずれ、小詩人(短歌も書いている)の僕の呟きである。
2015年12月25日 (金)
詩誌「角」第38号
 あわら市にお住まいの詩人、S・章人さんが、同人詩誌「角(つの)」第38号を送って下さった。
あわら市にお住まいの詩人、S・章人さんが、同人詩誌「角(つの)」第38号を送って下さった。
同誌37号は、今年9月15日の記事(←リンクしてある)で紹介した。
本号の執筆者は15名、17編。36ページ。
K・久璋さんの詩「嫁が涙」は、初連の中の「岩間隠れの石清水/だれが名づけたか/嫁が涙 もしくは涙水ともいう」の3行を発展させたものである。妻を泣かせた事のある夫に、痛みを覚えさせるが、展開は特異ではない。
S・章人さんの「お盆の墓参り」は、陸軍伍長として戦死した叔父の墓をめぐって、戦争の傷が風化する時代を描いている。
T・百代子さんが「角」誌に初めて、詩「仮設の隙間」を載せている。安住の場となるなら、佳い事だ。
ブログランキング
- 応援のクリックを、よろしくお願いします。
- ブログ村も、よろしくお願いします。
最近の記事
最近のトラックバック
- 第1回本屋大賞 1位:博士の愛した数式/小川洋子 (ナマクラ!Reviews)
- 夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2009 著/村上春樹 (あなたに必要な一冊 目次と紹介(ビジネス書評))
- 自分らしく生きるのは重要で、難しい:非属の才能 (本読みの記録)
- 日展見てきました (<インナーマッスル> 税理士 鈴木徹のブログ)
リンク集
ブログパーツ
- ツイートをフォローしてください。
- 3カウンター
- アクセス解析
更新ブログ
Member since 04/2007
日本ブログ村
- 日本ブログ村のリストです。
人気ブログランキング
- 応援の投票を、お願いします。



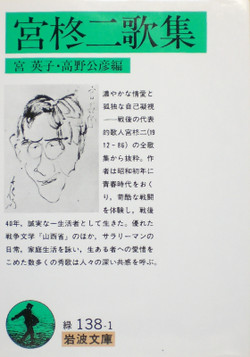




最近のコメント