平田利栄「海の駅舎」
2001年、雁書館・刊。445首。
彼女は「人」所属、「人」解散後は「滄」「華」所属。
父の死、老母のことを含め、生活を丹念に詠んで、好感が持てる。
語彙の斡旋がやや不得手のようで、自身も自覚しているが、類型的句がやや多いようだ。
たとえば「身じろがず待つ」「近ぢかと見ゆ」など。
40代に入って初めての教職に就く、郷里の老母を家に引き取る、など優しく頑張り屋の方のようで、先が待たれる。
以下に7首を引く。
廃線の枕木を焼く火の蒼し広場にひとりしやがみて目守(まも)る
本番に弱き男のものがたり読みつつ思ひ当たる人あり
ふるさとの昼間のバスに乗り込める多くは通院帰りの人ら
身をかたく教へ子の名前聴きてゐる卒業合否判定会議
縁ふかき順序に釘を回し打ち父の柩はつひに閉ぢらる
村人につひになれざる母に似て我も方言つかふことなし
沖縄の幹線道路走りゆくナンバープレートなき米軍車










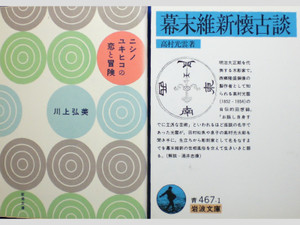


最近のコメント