カテゴリ「歌書」の467件の記事 
2012年12月26日 (水)
2012年12月24日 (月)
川辺古一「北枝」
1981年、石川書房・刊。
箱、題簽(本体の)・宮柊二、501首。
1975年(49歳)~1980年(54歳)の作品である。
氏の経歴については、第3歌集「駅家」を紹介した、このブログの2012年11月27日の記事を、参照されたい。
自然、社寺への旅行詠に氏は、平静というより沈潜した心境を見せる。
心の騒がしい僕は、畏怖さえ感じる。
以下に8首を引く。
紀三井寺急階段に息喘ぐわれを笑ひて老婆は立てり
松本の石仏群を見にゆきて三日も経つに子は帰り来ず
冷害を嘆く農夫と白河の関あといでて東へ向ふ
水槽の底に葛粉の固まるを鉄槌もちて人は割りゆく
乾きつつ白く光りて縁側に張子の馬の数頭ならぶ
弟の葬儀を見むとあつまりし少年達にキャラメル配る
七重八重石の仏にからみつき花咲かせをり定家かづらは
渓谷に秋の光の及ぶとき影のごとくに虹鱒泳ぐ
なお漢字の1部を、正字より略字に替えてある。
2012年12月22日 (土)
「コスモス」2013年1月号
結社歌誌「コスモス」2013年1月号を読みおえる。
ただし初めより、「その一集」特選欄までと、「COSMOS集」、「新・扇状地」、第59回O先生賞受賞作「時は返らず」「白蝶貝」、他。
僕が今回、付箋を貼ったのは、32ページ上段、「その一集」特選欄のHのりこさんの5首のうち、次の作品である。
おろしたての長袖シャツにGパンでやや秋めける原宿に来つ
東京の方だが、やや改まった気持ちで、原宿(地理オンチの僕は、生涯、訪れる事はないだろうな)に来た思いを述べている。
同誌はこれからも、読み続ける予定である。
2012年12月20日 (木)
伊藤麟「蛍まつり」
1980年(昭和55年)、伊麻書房・刊。
僕と氏との関わりは、「コスモス」2008-2月号の氏の追悼特集について書いた、このブログの2008年1月26日の記事を読んでいただきたい。
その誌も残っていないが、代表歌、年譜なども載っていたと記憶する。
「コスモス」では「螢」の字を用いる人が多い中、当時でも「蛍」の字を用いる、或は箱の歌集名を横書きにするなど、先進的な考えの歌人だったようだ。
また詩的な表現の短歌も多い。
写真は、箱の表である。染みが多くある。
以下に5首を引く。
つばらかに想ひ出せねど悔恨のわれのくれなゐ柘榴(ざくろ)咲きたり
前肢を揃へて水を舐(な)むる虎、年逝かむここ日本の園に
あはれなる絵島の墓に来て屈みさて立ち上がり四方(よも)の寂けさ
峰移る霧の微粒は顔を打ち押し黙りたり山上の九人
船と岸テープ投げ合ふ喚声の露語を解せず吾は異邦人
2012年12月19日 (水)
2012年12月12日 (水)
間島定義「鋼と杉」
昭和55年、白玉書房・刊。
箱、宮柊二・題簽、口絵1葉。
昭和38年~46年までの作品、508首を収める。
手許には、この歌集の外に資料がない。
新潟県より埼玉県に移住し、「コスモス」の編集に加わった。
作品に「草木盡心」といった境に近づくものを加えてみたいと願ったようだ。
以下に7首を引く。
ゆたかなる夏迎へをり野の先の青さうるめる麦の畑は
利根川の瀬鳴りとよむにひびきあひ寂しも空のまほら逝(ゆ)く風
木馬道(きうまみち)を黒く素早く走り去り山むささびは谷にひそみつ
うつうつと心沈む日雨後(うご)の山登りてくれば韮白く咲く
水走る這松の下黒百合のしづけき花の逝(ゆ)く春を咲く
樅の葉に結びし霧氷(むひょう)かすかなる輝き放つ尾根の樹海に
歌選ぶ仕事より立ち先生のふとなにごとか呟きますを
なお1部、正字より略字に変えてある。
2012年12月 5日 (水)
岡部文夫「石の上の霜」
 岡部文夫(1908~1990)の歌集、「石の上の霜」を読みおえる。
岡部文夫(1908~1990)の歌集、「石の上の霜」を読みおえる。
短歌新聞社、1977年・刊。683首。
写真は、箱の表。
岡部文夫はこののち、日本歌人クラブ賞、短歌研究賞、迢空賞、各賞受賞。
当時の彼は、福井県坂井郡(現・坂井市)に住んだ。僕の「コスモス」入会が1993年だから、彼の亡くなったあとである。
郷里の能登、福井の漁村の、厳しい環境に生きる老たちを描いて、情感がある。
以下に7首を引く。
寺ふたつ養ふに足る谷の村漆に冨みて今にゆたけし
北潟の水の寒鮒を煮むといふ聞きてゆふべを待つはたのしき
原電に潤ふ海の村といへど心けはしく荒(すさ)びゆくらし
隠すなき貧を互みに貶めて一つ入江には一つ村あり
生きるだけ生きて用なき媼らの熱き銭湯をただに楽しむ
日の長くなりしを言ひてしろたへの清き豆腐を掌(て)の上に切る
長く生きし二人の今日のよろこびに蒲生の海の皮剥を煮る
2012年12月 2日 (日)
東谷節子「明日の神話」
 東谷節子(ひがしたに・せつこ)さんの第1歌集、「明日の神話」を読みおえる。
東谷節子(ひがしたに・せつこ)さんの第1歌集、「明日の神話」を読みおえる。
2006年、短歌研究社・刊。青井史・帯文。
彼女は、1938年・生れ、1990年「雁来紅(かまつか)短歌会」参加、1995年「かりうど」(青井史・創刊)の創刊に参加、現在に至る。
夫の両親の老齢等により、西宮市で同居。娘の結婚、出産があり、舅の逝去、阪神大震災にも遭った。
それらを経るには、短歌の力も大きかっただろう。
イタリア・フランス・旧東独を訪う旅、風の盆への旅、9・11、イラク戦反戦運動なども、詠われている。
古典文法、新かな遣いを用いる。
以下に8首を引く。
嫁ぐ日の迫りて寡黙になりし娘は微笑むこと多し吾に対いて
「嫁からの義理チョコですが」と差出せば舅ははつかに笑み給うなり
父母と共に老いゆく明け暮れの夫の寡黙は病にも似る
面伏せて胎児を庇う娘には母なる仕草のすでに身につく
ローソクの芯の如くに病み細り舅は風熱き七月に果つ
舅という支柱失くせし姑の蔓宙に揺れいる如き危うさ
「しんどい」と言いつつ夫は足軽く二度目の勤めの朝を出でゆく
全身の骨の疼きに喘ぎつつ「もう死なして」と姉は言いにき(急性白血病)
2012年11月27日 (火)
川辺古一「駅家」
 川辺古一(かわべ・こいち、1926~)氏の第3歌集、「駅家(えきや)」を読みおえる。
川辺古一(かわべ・こいち、1926~)氏の第3歌集、「駅家(えきや)」を読みおえる。
1977年、伊麻書房・刊。
宮柊二・題簽、箱、本体にパラフィン紙カバー。
1966年(40歳)~1974年(48歳)の作品より、724首を収める。
氏は、1945年「多磨」入会、1953年「コスモス」創刊に参加。宮柊二への敬愛が篤かった。
自然を詠んだ歌が多いが、その中に自己・他者を押し出して、純粋な自然詠にならない。例えば「素枯れたる林の中に頸伸ばし雉一羽いまわが方を見る」のように。
以下に6首を引く。
これ以上乾く筈なき枯草に風音こもる昼間を歩む
山上の墓前に妻が供へたる牛乳壜に夕陽は当る
いきいきとわれを見給ふ神護寺の虚空菩薩の腕太しも
自動車の風圧の音いさぎよし校正終へて帰る夜道に
汗ひきてゆくを待ちつつ立ちをれば山畑の紫蘇焼く匂ひする
会議故今日も遅しと告げしとき妻よりも子は寂しき顔す
2012年11月26日 (月)
ブログランキング
- 応援のクリックを、よろしくお願いします。
- ブログ村も、よろしくお願いします。
最近の記事
最近のトラックバック
- 第1回本屋大賞 1位:博士の愛した数式/小川洋子 (ナマクラ!Reviews)
- 夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2009 著/村上春樹 (あなたに必要な一冊 目次と紹介(ビジネス書評))
- 自分らしく生きるのは重要で、難しい:非属の才能 (本読みの記録)
- 日展見てきました (<インナーマッスル> 税理士 鈴木徹のブログ)
リンク集
ブログパーツ
- ツイートをフォローしてください。
- 3カウンター
- アクセス解析
更新ブログ
Member since 04/2007
日本ブログ村
- 日本ブログ村のリストです。
人気ブログランキング
- 応援の投票を、お願いします。


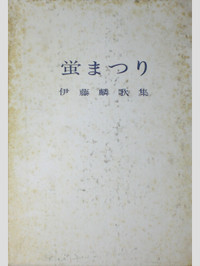




最近のコメント