石原吉郎「いちまいの上衣のうた 1967」
花神社「石原吉郎全詩集」(1976年・刊)より、2番めの詩集「いちまいの上衣のうた」を読みおえる。
先の10月27日、第1詩集「サンチョ・パンサの帰郷」を紹介した記事に、続くものである。
この詩集(1964年~1967年に、詩誌に発表された、52編を収録)には「1967」と年号が付されるが、次に載る「斧の思想」と共に、全詩集の巻末の「著作目録」にも、ウィキペディアの「石原吉郎」の項目にも、不載である。詩集の経緯の詳細を、僕は知らない。
過去と現実、経験と言葉を、うまく折り合わせられなかった詩人が、現実を生活してゆこうとする意志が見える。
詩「いちまいの上衣のうた」では、「いかなる日におれが/指と指ぬきを愛したか/条理をくり展(の)べては/やさしげな火をかき起し……まさにそのことのゆえに/愛はひたすらに町をあふれ/帆のようにおれは/夕暮れをはらむのだ」と謳う。
また詩「欠落」では、「およそ欠落においてのみ/あたたかな手でとりもどす/この寂寥は/信じなければならぬ」と、信じ得ると書いた。
次の詩集「斧の思想 1970」では、敵と死が描かれるとしても。
本文とは無関係。



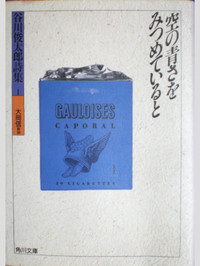







最近のコメント