カテゴリ「詩集」の190件の記事 
2013年2月24日 (日)
2013年2月 9日 (土)
神子萌夏「白をあつめる」
 県内にお住まいの詩人・神子萌夏さんの詩集、「白をあつめる」を、詩誌仲間・AUさんを通して受け取った。
県内にお住まいの詩人・神子萌夏さんの詩集、「白をあつめる」を、詩誌仲間・AUさんを通して受け取った。
2013年、ジャンクション・ハーベスト・刊。
ビニールカバー装だが、光の反射が強いので、写真では外してある。
「透き通ってゆく午後」、「植物系」に続く、彼女の第3詩集である。
作品「ひこうき雲」の第3連に「ふつかごとにリセットされるいのち/フィルターで濾過される/わたしの日々のいとなみ」とあるように、彼女は週3日の人工透析を受けている。
だから彼女は、生命にとても敏感だ。
「約束」で受胎を歌い、「草の香り」でバッタの余命を気遣う。
「ことばを探して」は、豊かなレトリックを用いた、優れた作品である。全6連の最終連のみを引く。
「ことばを探して」より
ことばは増えたのにうまく取り出せなくて
いまもわたしの海のなか
ひかる小魚たちが
ぐるぐるまわっている
2012年12月15日 (土)
石原吉郎「満月をしも」
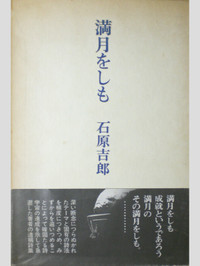 一昨日に続き、石原吉郎の遺稿詩集「満月をしも」を読みおえる。
一昨日に続き、石原吉郎の遺稿詩集「満月をしも」を読みおえる。
1978年、思潮社・刊、箱、帯補。
先の12月11日の記事で、購入報告した本である。
なお彼は、1977年に急死した。
彼をめぐっては、この帯にもあるように、「断念」とよく言われるけれども、内容やいきさつは、詩からのみではわかりにくい。
評論等も含めた、彼の3巻本全集が、花神社から出ているが、ネットの「日本の古本屋」で見ると数万円もの値がついて、僕にはとても買えない。
彼の作品に接すると、接しない人とは、人生が変わる、と複数の文学者が書いている。僕ももっと早く、彼の作品を読むべきだったのだろうか。
彼の短い詩「影」全文を引く。
影
あとへ曳くなら曳かせておけ
横へ曳いたら
横へ曳かせろ だが
その影に
「寂しい」とは
一と言も言わせるな
2012年12月13日 (木)
石原吉郎「足利」
 石原吉郎(いしはら・よしろう)の詩集、「足利」を読みおえる。
石原吉郎(いしはら・よしろう)の詩集、「足利」を読みおえる。
花神社、1977年・刊。箱、帯。
短い詩が多く、40編を収める。
これまで紹介してきた「石原吉郎全詩集」の終いの詩集「北條」に継ぐ詩集である。
折り目正しい、礼儀に篤い、彼の境地が表されている。
1編の短さ、1行の短さは、彼が関わった句作の影響があるかも知れない。
俳句の短い定型、季語のしばりでは、思いを述べることは難しい(?)。彼の、言外の思いを汲み取ってもらいたい、という詩作法は、それからも来ているようだ。
彼の短い詩「一期」全文を紹介する。
一期(いちご)
一期にしてついに会わず
膝を置き
手を置き
目礼して ついに
会わざるもの
2012年12月11日 (火)
2012年12月 8日 (土)
石原吉郎・未刊詩篇
花神社「石原吉郎全詩集」(1976年・刊)より、「未刊詩篇」を読みおえる。
「Ⅰ 文章倶楽部・ロシナンテから(8編)」と「Ⅱ シベリヤ詩篇から(4編)」の2つに分かれる。
「文章倶楽部」は投稿文芸誌だったらしく、「ロシナンテ」は1955年創刊の同人詩誌である。初出が彼の第1詩集「サンチョ・パンサの帰郷」の詩と重なる作品があるが、篩い分けの基準は僕にはわからない。
「古い近衛兵」の末4行を引く。
古い近衛兵(前略)
われらはたえまなく
雨によごれたひげをひねり
はみだした勇気をおしこんでは
不発の衝動をひきよせる
「シベリヤ詩篇」は、抑留時代に創って記憶していた作品を、書き残したものである。文語調の詩である。
「裸火」全5行を引く。
裸火( 一九五二年 ハバロフスク)
われやはらかき
手のひらもて
風に裸火をふせがん
またたける
いのちを掩はん
生前の全詩集だったので、このあと2詩集がある。「足利」は所有しており、最後の詩集「満月をしも」は取寄せ中である。
2012年12月 3日 (月)
石原吉郎「北條」
花神社「石原吉郎全詩集」(1976年・刊)より、6番めの詩集「北條」を読みおえる。
原著は、1975年、花神社・刊。
先の11月29日に紹介した、「禮節」に続く詩集である。
石原吉郎(1915~1977)にはこのあと、「足利」「満月をしも」の2詩集がある。
全詩集に載る、最後の詩集である。このあと、句集と未刊詩篇等を収める。
「北條」では、「一條」「北條」から始まる散文詩で、語感に頼りながら、詩を成り立たせている。
彼の郷愁が満たされた(彼の思いと、戦後日本の心情・風土には違和があったようだ)時期か。しかし言葉の上でだけの事かも知れない。
「痛み」という散文詩で彼は、「 最後に痛みは ついに癒されねばならぬ」と書く。最後まで癒されぬ痛みもあるだろうに。
本文とは無関係。
2012年11月29日 (木)
石原吉郎「禮節」
花神社「石原吉郎全詩集」(1976年・刊)より、5番めの「禮節」を読みおえる。
原著は、1974年、サンリオ出版・刊。
先の11月19日に紹介した、「水準原点」に続く詩集である。
冒頭の作品「断念」には、シベリア抑留時代の考えと、日本での生活の考えを、切り離そうとするようだ。初めと終わりを引くと、次のようである。
この日 馬は
蹄鉄を終る
あるいは蹄鉄が馬を。
(中略)
馬は脚をあげる
蹄鉄は砂上にのこる
「犯罪」では、言葉の意味やイメージから、語感の詩へ移る、と宣しているようだ。初めの3行のみ引く。
音楽であるために
かくもながい懲罰を
必要とした
(後略)
「闇と比喩」では、彼の詩の出発が、戦後詩の主流であった、比喩に比喩を重ねるような手法を、採らなかった理由を示すようだ。末尾の4行を引く。
(前略)
比喩とはならぬ
過剰なものを
闇のかたちへ
追い立てながら
このあと彼は、後期の「北條」「足利」の詩集へ、移って行く。
2012年11月19日 (月)
石原吉郎「水準原点」
花神社「石原吉郎全詩集」(1976年・刊)より、4番めの「水準原点」を読みおえる。
原著は、1972年、サンリオ出版・刊。
石原吉郎は、シベリア抑留を体験する事に由って、詩人となった。
戦時日本の、シベリア抑留の、戦後日本の、倫理を問い続けて、人間的であった。
彼のその後の詩と、彼の散文を読んでいない(彼の全3巻の全集に含まれる)ので、その心の経緯を僕は語れない。
以下に、彼の短めの詩を1編、丸ごと紹介する。
右側の葬列石原吉郎
その右側の葬列のためひたすらに その
ひだりがある
ひだりへ流れる
布の蒼白がある
蒼白のための
わずかな紅(くれない)がある
紅を点ずる
さいごの仕草がある
仕草をおさえる
おしころした手がある
その手ではじまる
葬列の右側がある
本文とは無関係。
2012年11月13日 (火)
石原吉郎「斧の思想」
花神社「石原吉郎全詩集」(1976年・刊)より、3冊めの「斧の思想」を読みおえる。
彼は「残り火・1」の冒頭「そのひとところだけ/ふみ消しておけ/そういう/ゆるしかたもある」と書いたが、モチーフであろうシベリア抑留が「許される」事ではなかった。ソ連が崩壊し、その理念も崩壊した。
表題作の「斧の思想」では、「森が信じた思想を/斧もまた信じた/斧の刃をわたる/風もまた信じた」と語る。何にでも哲学はある。「斧の思想」が、シベリヤでの森林伐採使役を合理化しようとするものなら、のちの世代の僕らは、否定し得る。
「背後」では、「打つものと/打たれるものが向きあうとき/左右は明確に/逆転する/わかったな それが/敵であるための必要にして/十分な条件だ」と書いて、敵対の原型を描いた。
彼は詩を書き、許す事に拠って、許されたのだろうか、ソ連崩壊も知らずに。
本文とは無関係。
ブログランキング
- 応援のクリックを、よろしくお願いします。
- ブログ村も、よろしくお願いします。
最近の記事
最近のトラックバック
- 第1回本屋大賞 1位:博士の愛した数式/小川洋子 (ナマクラ!Reviews)
- 夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2009 著/村上春樹 (あなたに必要な一冊 目次と紹介(ビジネス書評))
- 自分らしく生きるのは重要で、難しい:非属の才能 (本読みの記録)
- 日展見てきました (<インナーマッスル> 税理士 鈴木徹のブログ)
リンク集
ブログパーツ
- ツイートをフォローしてください。
- 3カウンター
- アクセス解析
更新ブログ
Member since 04/2007
日本ブログ村
- 日本ブログ村のリストです。
人気ブログランキング
- 応援の投票を、お願いします。


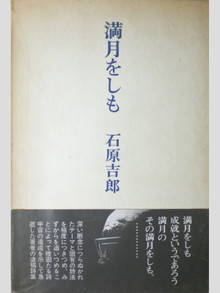




最近のコメント